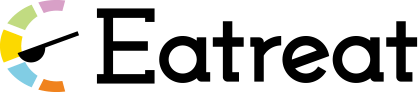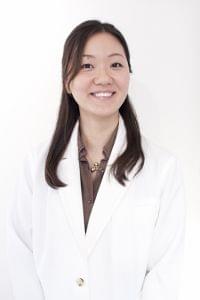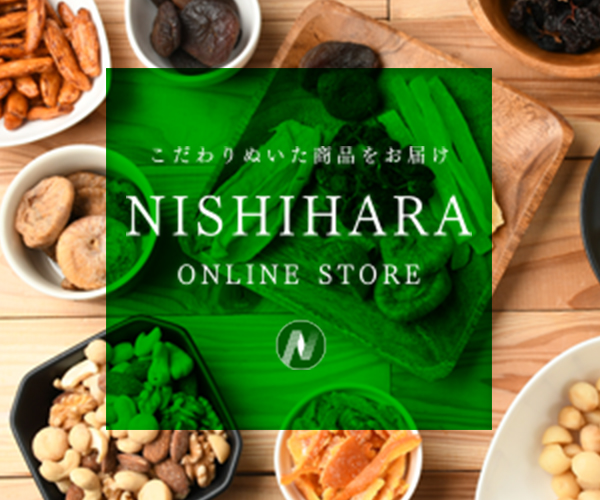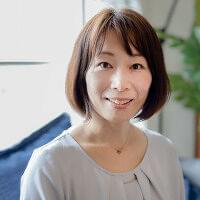薬膳の本場中国の医療事情
中医学の本場、中国の病院では中医学と西洋医学のどちらも扱っている「中西医結合医療」が一般的です。看板に「中医病院」と書いていても、実際は西洋医学の治療しかしない場合もあります。たとえば、医師がその患者には中医学の治療よりも西洋医学の治療の方が相応しいと判断すれば、中医学治療を行いません。ただ、内服薬や点滴、浣腸薬に至るまで、西洋医学の治療で使う製剤の中にも生薬が含まれている物が一般的ですので、厳密に分離されてないという方が正しいのかもしれません。
中国ではカルテやレントゲン、検査結果を患者自身が保管しています。病院が変わっても、どこでどんな治療を受けてきたか、などの情報はすぐに分かるので、非常に合理的なシステムです。
薬膳の本場中国の健康問題
近年、上海や北京など中国の大都市では、経済成長と共に、日本がすでに歩んできたのと同様に「食のコンビニ化」が急速に進んでいます。私が生活を始めた2001年の北京には、コンビニは数えるほどもなく、冷凍食品なんて町のレストランより高く、味も落ちるので、利用する人も少なかったのですが、今や街にはコンビニや24時間営業のファストフードがあふれ、料理の宅配サービスも24時間営業が当たり前です。
中国でも10年ほど前から急速に肥満児の姿を見るようになり、危機感を感じた記憶があります。私は食の欧米化云々より、食のコンビニ化が肥満をはじめとする「食原病」の原因だと考えています。
とは言え、中国では薬膳の考えもしっかり残っていて、女性が冷たいドリンクをがぶ飲みする姿を見かけることはありません。一般の人でも、どんな時にどんな物を食べるとよいかをよく知っています。このまま本場の智慧を守って欲しいと願うばかりです。
今や糖尿病大国の中国、次回は中国の栄養士について書きたいと思います。
おすすめコラム
薬膳って何?
薬膳学と栄養学の違いと相性
薬膳初心者のための薬膳の考え方と基礎理論① 陰陽学説と食べ物の四性について
薬膳料理と精進料理はどう違う?