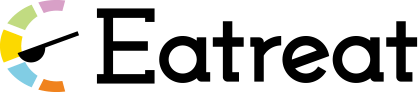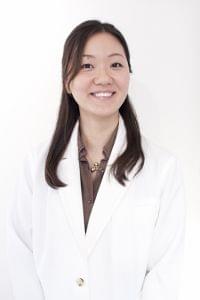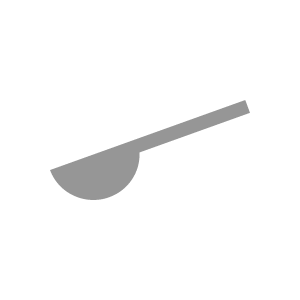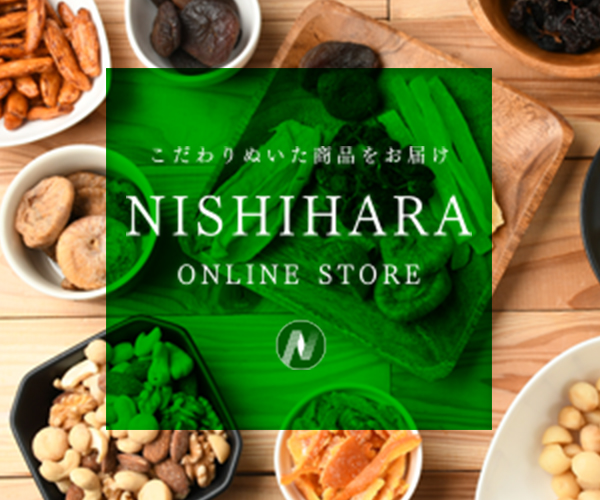眠気を誘う春の気候
中国の古い詩に「春眠不覚暁(しゅんみんあかつきをおぼえず)」という一節がありますが、春の暖かい気候は眠気を誘い、朝になってもなかなか起きられず、ついつい寝すぎてしまいます。日本では、春は新年度を迎える時期ですが、だるくてやる気が起きないという状態になったり、精神的にも鬱になりやすくなったりする時期でもあります。
春の眠気は季節のせいだけではない
春の眠気は、季節的な要因だけではなく、単に睡眠不足や疲労、無呼吸や甲状腺のトラブルなどが原因であることも考えられます。眠気のほとんどは、冬の間に食べ過ぎて、體(からだ)に老廃物や余分な水分を溜め込んでしまい、さらに寒いからと運動せずにいたことが原因です。春になると芽吹く苦味のある山菜には、解毒作用があるので、やはり旬の食材を食卓に取り入れることが大切です。
中医学的にみると、「季節の薬膳を組み立てる(春の特徴と薬膳)」でお話しましたが、春は肝の氣が上がりやすい季節です。肝の氣が強く働き過ぎると、脾(消化器)を傷めます。脾の働きが弱ることで、体内にある余分な水分が追い出されず、體が重く、特に食後に眠くなります。脾が弱ると、花粉症などのアレルギーの原因にもなります。冬に無茶をした人は腎が弱り、水の代謝機能が落ちているので、むくみや尿トラブル、老化なども現れます。
春は眠気に負けず、早起きすること
「黄帝内経」には、「春は眠いからと遅くまで寝ていないで、無理してでも早起きする方がよい」と書かれています。そして食事は、胃腸にやさしい食事を心がけてください。締め付ける服装や薄着も避けましょう。香りの良い野菜やフルーツ、アロマなどを取り入れ、適度な運動をして氣のめぐりを良くすることも大切です。
関連コラム
季節の薬膳を組み立てる(春の特徴と薬膳)
薬膳の本場中国の医療事情と健康問題
中医学とは?