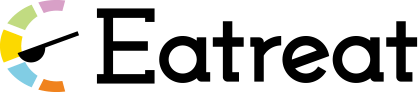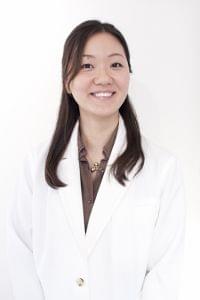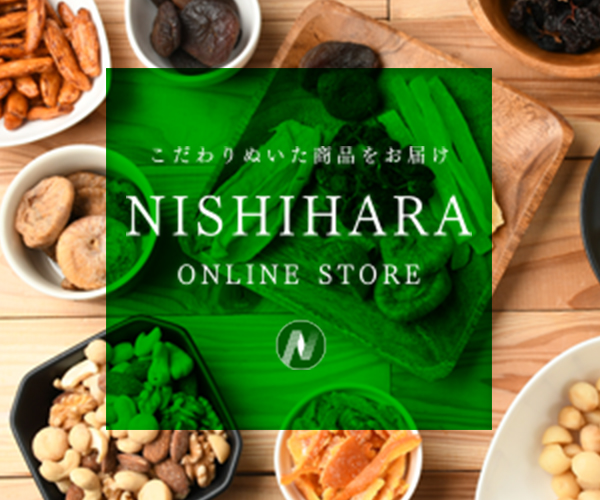以前、「色で選ぶ薬膳学 - 食べ物の色のチカラを知ろう」について執筆しましたが、今回は「味」についてのお話です。まずは五行学説のつながりを復習してみましょう。
臓腑と味のつながり
木火土金水それぞれの色と季節や臓腑のつながりを見てみると、次のようになります。
■木―春―青―肝―胆―酸
■火―夏―赤―心―小腸―苦
■土―長夏(梅雨)―黄―脾(消化機能)―胃―甘
■金―秋―白―肺―大腸―辛
■水―冬―黒―腎―膀胱―鹹(塩からい)
上記は、肝と胆は酸味、心と小腸は苦味、脾と胃は甘味、肺と大腸は辛味、腎と膀胱はしおからい味を好むと読み解くことができます。
5つの味を取り入れよう
各味に当てはまる食材は、次の通りです。
中医・薬膳で言う「味」は、食べて感じる味覚だけでなく、その味の持つ働きのことも指しています。そのため、本の表記と食べた時の実際の味と異なることもあります。
◇酸味(體を引き締め、体液を生む。血液をきれいにする)
酢、レモンなどの柑橘類、トマト、サンザシ、ヨーグルト、果物など。
◇苦味(体内の不要な水分や炎症を取り除く)
ゴーヤ、コーヒー、お茶、山菜や野草、ごぼう、グレープフルーツ、ビールなど。
◇甘味(疲れを癒し、リラックスさせる)
米類、いも類、栗、なつめ等のドライフルーツ、大豆、果物、砂糖など。
◇辛味(発汗させ、氣のめぐりを良くする。體を温める)
スパイス類、ネギ、玉ねぎ、にんにく、生姜、酒など。
◇鹹味(体内に溜まった不要物を追い出し、固まりをほぐす)
味噌、醤油、塩、海藻類、きのこ類、魚介類など。
酸っぱい物を食べると唾液が出て體が引き締まる感じがしたり、甘い物ではホッとしたり、その味を感じた時の肉体の反応を観察してみてください。
1つの味に極端に偏らないように、いろんな味を取り入れてみましょう。
関連コラム
・薬膳って何?
・薬膳学と栄養学の違いと相性
・薬膳初心者のための薬膳の考え方と基礎理論① 陰陽学説と食べ物の四性について