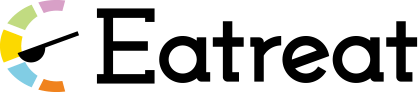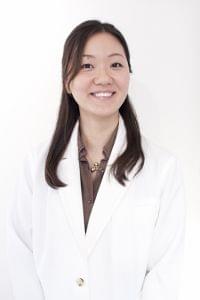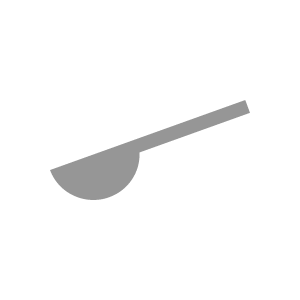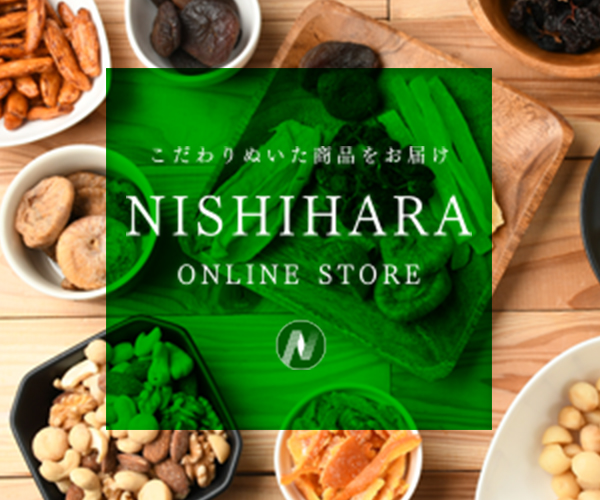五行学説の実践
中国古代の哲学から生れた「五行学説」は、地球上に存在する5つの要素「木火土金水」の性質に、季節や臓腑、感情、方角、色、味、匂い、音などを当てはめてさまざまな分析や決定をしていく学問の1つです。
薬膳の世界には、その五行学説をもとに臓腑(内臓)と色・臓腑と味などのつながりに注目した食事方法が基本としてあります。今回は臓腑と色のつながりについて説明をします。

臓腑と色のつながり
木火土金水それぞれの色と季節や臓腑のつながりを見てみると、次のようになります。
■木―春―青―肝―胆
■火―夏―赤―心―小腸
■土―長夏(梅雨)―黄―脾(消化機能)―胃
■金―秋―白―肺―大腸
■水―冬―黒―腎―膀胱
上記は、肝と胆は青(植物の葉の色)、心と小腸は赤、脾と胃は黄、肺と大腸は白、腎と膀胱は黒を好むと読み解くことができます。
5つの色のチカラを取り入れる
各色に当てはまる食材は次の通りです。
◇青―ほうれん草、小松菜、ブロッコリ―、春菊、セロリ、緑茶など。
◇赤―なつめ、クコの実、トマト、人参、クランベリー、赤ワインなど。
◇黄―とうもろこし、かぼちゃ、じゃがいも、大豆、きび、黄花菜など。
◇白―白米、大根、かぶ、れんこん、白きくらげ、百合根、白ゴマなど。
◇黒―黒きくらげ、しいたけ、昆布、黒ゴマ、黒豆、黒米、など。
まずは五臓に「色のチカラ」をまんべんなく取り入れてみましょう。知識が深まってくると、ストレスで肝が弱っている時は緑茶でホッと一息つくとよいとか、神経が高ぶってイライラする時はなつめを食べるとよいといった、現代医学や民間療法などで言われていることの根拠が見い出せるとともに、その時々の体の状態に合せてどんな食べ物(飲み物)を選べばいいかという「選択力とバランス力」も身に付くことでしょう。
関連コラム
薬膳って何?
薬膳学と栄養学の違いと相性
薬膳初心者のための薬膳の考え方と基礎理論① 陰陽学説と食べ物の四性について