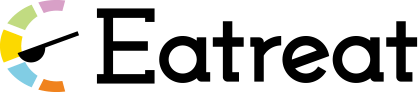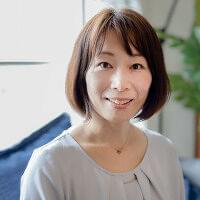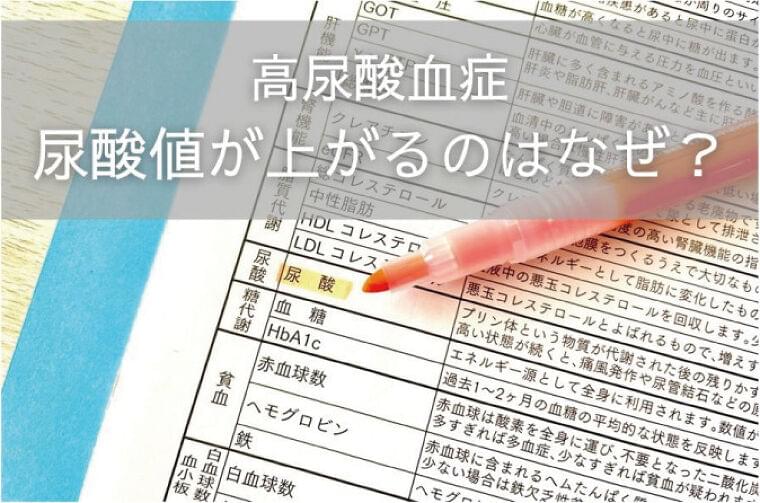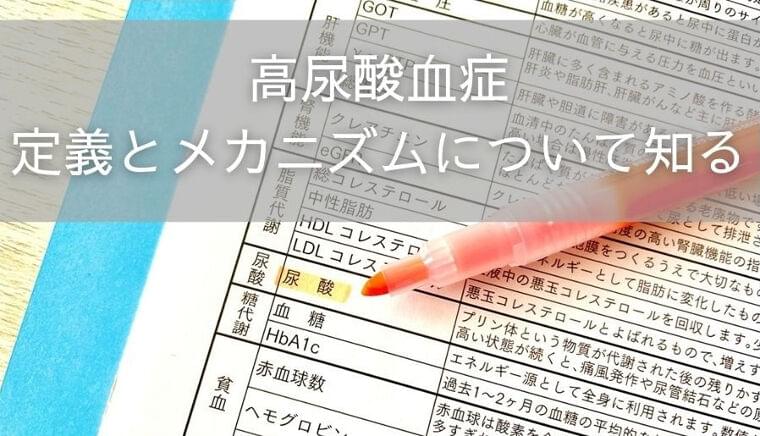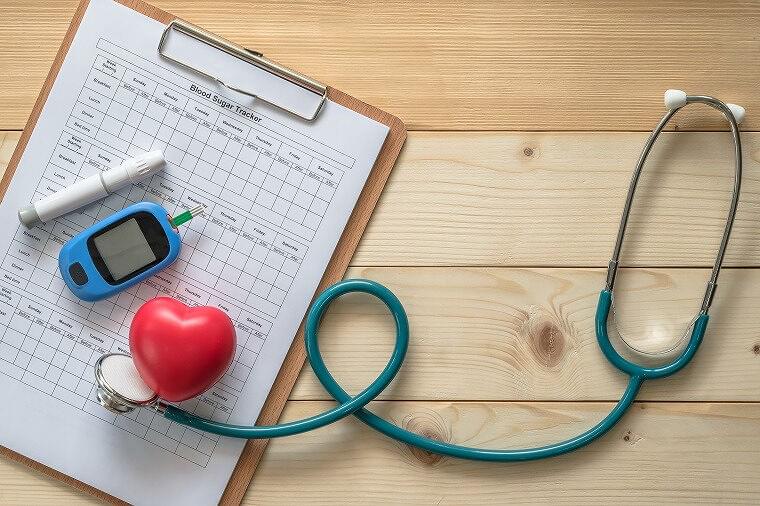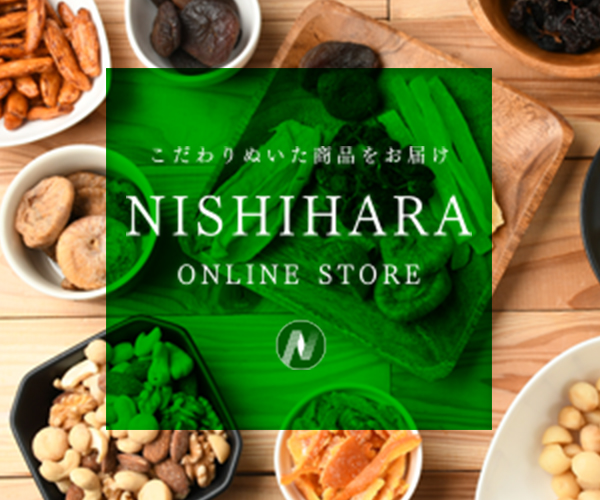高血圧症は、自覚症状のない病気です。
「血圧が高い」と言われてもどのような状態なのかをイメージするのは難しいですよね。
そんな高血圧症について3回に分けて詳しくご紹介します。
血圧とは? 定義とメカニズム
血圧とは、血液が血管壁に与える血管内圧のことで、一般的には動脈の内圧を指します。
動脈内圧の最高値を収縮期血圧、最低値を拡張期血圧といいます。
血圧は、心臓が動脈を通して全身に血液を送り出すための圧力でもあり、「心拍出量(心臓から拍出される血液の総量)×末梢血管抵抗(血管内での血液の流れにくさ)」で表すことができます。

血圧を上昇させるホルモンと低下させるホルモン
私たちのからだの中では、血圧を一定範囲に保ち全身の血流を維持するために、自律神経による神経性調節、ホルモンなどの液性因子による液性調節が働いています。
▶神経性調節
神経性調節を担うのは自律神経であり、交感神経と副交感神からなります。
交感神経が興奮すると血圧が上昇し、副交感神経が興奮すると血圧は低下します。
▶液性調節
血圧調整には、さまざまなホルモンの働きが関わっています。
腎臓でのNa+の再吸収が促進すると体液量(循環血液量)が増加し、血圧が上昇します。逆に再吸収が抑制されると体液量は減少し、血圧は低下します。

降圧剤の種類と特徴
上述のメカニズムから、血圧を下げるためには「体液量をコントロールする」ことと「血管抵抗をコントロールする」ことが必要です。降圧剤は、それぞれの作用または両方の作用をもつものがあります。

まとめ
血圧の定義とメカニズムについてご紹介しました。
次回は、曖昧になりがちな血圧の基準値や考え方についてお伝えします。
参考文献
・「からだがみえる 人体の構造と機能」、株式会社メディックメディア出版、(2023年)
関連コラム
・肥満症とは?肥満の定義とメカニズムを知る
・糖尿病とは?原因についてわかりやすく解説します