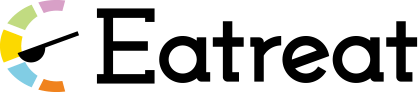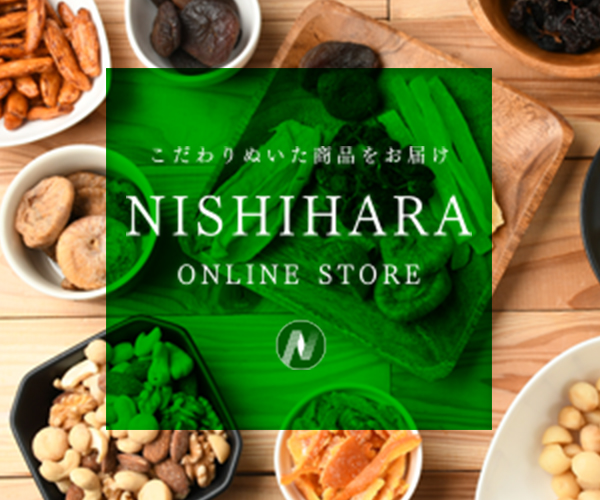年齢を重ねると体内の水分量は減少し、脱水のリスクが高まります。
今回のコラムでは、高齢者はなぜ脱水になりやすいのか分かりやすく解説します。
加齢と共に変化する体内の水分量
私たちの体は約60%が水分で構成されています。この水分は、血液として全身に栄養を運んだり、体温を調節したり、老廃物を排出したりと、生命維持に欠かせない役割を担っています。
しかし、年齢を重ねるごとに体内の水分量は徐々に減少していきます。成人では体重の約60%が水分であるのに対し、高齢者では50%以下にまで減ることもあります。そのため、仮に高齢者の方が若年成人と同じ量の水分を失ったとしたならば、元々体内にある水分量が少ないので簡単に脱水に陥ってしまいます。これが高齢者が脱水状態に陥りやすい主な原因となります。
脱水症状とは
そもそも「脱水症状」とは、体内から必要以上の水分や電解質が失われ、正常な生理機能が保てなくなる状態を指します。軽度の脱水では、喉の渇きや口の乾き、倦怠感などの症状が現れますが、進行すると頭痛、めまい、意識障害、さらには命に関わる深刻な健康被害へとつながることもあります。特に暑い季節や発熱時、下痢・嘔吐を伴う病気の際には水分とともにナトリウムやカリウムなどの電解質も失われやすく、注意が必要です。
高齢者が脱水状態に陥りやすい理由
高齢者が脱水に陥りやすい理由は多岐にわたります。
まず第一に、加齢により「喉の渇き」を感じにくくなることが挙げられます。体内の水分が減っても、それを脳が感知しにくくなり、自発的な水分摂取が減少してしまうのです。また、腎機能の低下により、尿を濃縮する能力も衰え、体内に水分を保持しづらくなります。さらに、高齢者は持病の影響で利尿剤などの薬を服用していることが多く、これも体内の水分を排出させる要因となります。他にも、認知機能の低下や身体機能の衰えにより、のどの渇きを感じても自分で水を取りに行けなかったり、飲むことを忘れてしまうケースも少なくありません。
高齢社会が進む中、脱水による救急搬送や入院は珍しいことではなくなっています。高齢者本人だけでなく、家族や介護者、医療・福祉の現場が一体となり「水分補給は命を守る基本のケア」であるという意識を共有することが求められています。
加齢によって体は確実に変化していきます。その変化に気づき、適切に対応することこそが、健康で豊かな老後を支える鍵となるのです。
参考文献
・日本病態栄養学会「病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイドブック」 第8版、南江堂、(2025)
・一般社団法人日本栄養治療学会「日本臨床栄養代謝学会JSPENテキストブック」南江堂、(2024)
・「脱水」、MSDマニュアル家庭版、https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/12-%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%81%A8%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E6%B0%B4%E5%88%86%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9/%E8%84%B1%E6%B0%B4、(閲覧日:2025年6月1日)
関連コラム
・高齢者が低栄養にならないために
・おさえておきたい糖尿病患者の水分補給のポイント